ミュニシパリズム、岸本聡子 岸本さとこ
岸本さとこさん 現杉並区長に当選前の研究論文。
ミュニシパリズム(トランスナショナル研究所研究員 岸本聡子)
季刊『社会運動』2022年1月発行【445号】特集:代理人運動と生活クラブ―民主主義を終わらせないより引用。
地域の主権を大切にする運動、ミュニシパリズムが世界各地で広がる
「ミュニシパリズム」という聞きなれない言葉を紹介し始めて、数年が経つ。ミュニシパリズムは、各地各国で多様性があるし、現在進行形で日々進化・深化しているので表現が難しいが、それでも私が社会運動の中で見たり、学んできたことを共有したい。
ミュニシパリズムは地域の主権を大切にする新しい政治運動だ。アルゼンチン、スペイン、イタリアなどから広がり、フランス、東欧でも勢いをつけている。イギリスやアメリカではミュニシパリズムよりも「ミュニシパル・ソーシャリズム」という言葉が使われることが多いようだ。文字通り地方自治体主導のソーシャリズムで、1800年代後半に個人の手中にあったガス、水道、下水などのインフラを公衆衛生向上のために自治体の管理下にした実践と運動がそのルーツ。現在に至る自治体の公共サービスの基盤を作った。日本語では「都市社会主義」と言われる。
その後1980年代からは新自由主義が強化され、深化した今に至る40年となる。最後の砦の公的な分野、例えば医療、教育、上下水道、電力、介護、保育、公園や図書館、ゴミ回収などの自治体サービスが、さまざまな形の民営化の波に侵食されてきた。その反動で、ヨーロッパを中心に再公営化運動、つまり一度民営化されたりアウトソースされたサービスを、公的な管理とオペレーションに戻すことが起きている。100年以上前の公営化運動と精神は共通で、住民の生命と健康を守り、福祉を向上させることだ。公共サービスの再公営化はミュニシパリズムの具体的な行動の一つであるが、もちろんそれだけではない。この原稿では、地域から積極的な民主主義と政治の性質そのものの根源的な変革を志向する、今の時代のミュニシパリズムに迫る。
(p.9-P.12 記事抜粋)
—
マガジン9、第1回:ミュニシパリズムとヨーロッパ その1(岸本聡子)
いま、ヨーロッパでは、バルセロナ(スペイン)、ナポリ(イタリア)、グルノーブル(フランス)などの革新的な勢力が市政につく自治体が「ミュニシパリズム」(municipalism)という言葉を掲げてつながりを強めている。
地方自治体の意である「 municipality 」から来ているミュニシパリズムやミュニシパリストは、政治参加を選挙による間接民主主義に限定せずに、地域に根付いた自治的な民主主義や合意形成を重視するという考え方だ。ミュニシパリズムを掲げる自治体は、市民の直接的な政治参加、公共サービスの再公営化や地方公営企業の設立、公営住宅の拡大、地元産の再生可能エネルギー、市政の透明性と説明責任の強化といった政策を次々に導入している。
昨年11月にEU議会内で開催した「Municipalize Europe!」(ヨーロッパをミュニシパリズムで民主化する!)と題する討論会には、バルセロナ、ナポリ、グルノーブルに加え、アムステルダム(オランダ)、パリ(フランス)、コペンハーゲン(デンマーク)、ルーベン(ベルギー)の副市長、市議たちが登壇した。いずれも近年の選挙で与党となった議員たちだ。
この討論会は、トランスナショナル研究所、コーポレートヨーロッパオブザーバトリー(CEO)、バルセロナ・コモンズ(Barcelona En Comú)(※)が、EU議会の政治会派グリーングループ・欧州自由同盟の協力を得て、2018年11月6日、ブリュッセルの欧州議会内で行ったもの。ミュニシパリズムは現在進行形の新しい政治、社会運動で日々成長しているため体系的に説明するのは難しい。この討論会での議論を紹介しながら理解を深めていきたい。
※CEO:ブリュッセルを拠点にEUの政策決定におけるビジネスロビーの独占的影響を監視し、民主化を求める調査・キャンペーンNGO。
※バルセロナ・コモンズ:経済危機下での住民の住居強制退去などと闘い市民の社会的権利を拡大するために結成した市民連合で2015年の地方選挙でバルセロナ・コモンズとして候補者を擁立。草の根の選挙運動で第一党となった。反貧困、住居の権利の活動家アーダ・コラウ(Ada Colau)が市長となった。
「市場よりも市民を優先」イタリアでの実践
1988年生まれのエラアノラ・デ・マヨは、2016年の選挙でナポリの市議になった。違法な債務問題に取り組んできた活動家で「民主主義と自治党」(DemA)の所属だ。DemAは現ナポリ市長ルイージ・デ・マギストリスが設立した政党。2011年に当選して以来、「コモンズ」(※)を政治の中心に据え、参加型民主主義を実践してきた先駆的な存在である。
※コモンズ:構成員によって共同で利用・管理される共有財や資源。水や土地といった自然から贈り物、共有資産、文化や知識といった創造物までが含まれる。
イタリア市民は公営水道の一部民営化を強制する法律を覆すために、2011年に国民投票を組織し歴史的な成功を勝ち取った。これによって水道事業から利益を上げることを禁止する憲法改正にこぎつけたが、多くの自治体がその精神に従わず利益追求型の水道サービスの形態を変えなかったので、市民の怒りと失望は大きい。そのような背景がある中で、マギストリス市長率いるナポリ市は、全国に先駆けて水道サービスの公的所有を確立し、水をコモンズ・公共財と位置付けた改革を行った。
マヨはミュニシパリズムをこう説明する。
ミュニシパリズムの自治体は「利潤と市場の法則よりも市民を優先する」という共通の規範を共有している。その意味は、社会的権利の実現のために政治課題の優先順位を決めること、新自由主義を脱却して公益とコモンズの価値を中心に置くことである。
公共サービスの公的所有を推進する、普通の人が払える住宅の提供と価格規制をする、環境保全と持続可能なエネルギーを推進するといった具体的な政策がミュニシパリズムの自治体には共通している。 とはいえ、そうした革新的な政策だけが目的ではない。創造的な市民の政治参加によって市民権を拡大する過程を重視する。さまざまな方法で直接民主主義的な実験を積極的に行っている。
バルセロナは「ミュニシパリズム」の先駆的存在
昨年12月30日のニュースによると、市は100件目となる市立保育園の設置を実施。27日のニュースは市が22件目となるアパートの買い取りを行い、いままでで最大規模の114世帯が入居できる公営住宅が誕生したことを伝えた。バルセロナ・コモンズが市政を担当してから、合計で8,960世帯の公営住宅を新たに供給できたことになる。その他にも低所得世帯が利用できる公営の葬儀サービス会社の設立、ドメスティックバイオレンス被害者救済サービスの再公営化、地元産自然エネルギー供給公営企業(Barcelona Energia)を設立し軌道に載せている。
討論会に登壇した、バルセロナ・コモンズの知的支柱でもある第一副市長ジェラルド・ピッサレロはこう語る。
2015年の選挙のとき、活動家として行動してきた私たちの多くは従来の政治体制を変える挑戦に挑むにあたって、具体的に人々の生活を改善するミュニシパリズムが最良の武器になると信じ、そして勝利した。
私たちは恐れと緊縮財政の政治に代わる、創造的で確かなオルタナティブを自治体から実践してきた。政治の優先課題を変え、地域経済への投資、各地区の予算の増加、不安定雇用を減らすこと、住民を住宅立ち退きから守ること、科学と技術イノベーションの強化、水やエネルギーといった公共財を守ること、大気汚染の削減などを真摯に、そして効果的に行ってきた。
ピッサレロは、経済の民主化、連帯、ミュニシパリストビジョンとその国際連携によって極右の台頭に対抗することを提案する。この国際主義こそ、ミュニシパリストが地域的な保護主義と一線を画する最大の特徴である。
このミュニシパリストが国際連携しネットワークするという考えを、バルセロナは2016年に「フィアレスシティ」( Fearless City/恐れない自治体)の設立を呼びかけることで成功させた。フィアレスシティは、抑圧的なEU、国家、多国籍企業、マスメディアを恐れず、難民の人権を守ることを恐れず、地域経済と地域の民主主義を積極的に発展させることで制裁を受けることを恐れないと謳う、住民と自治体の国際的なネットワークだ。2018年はニューヨーク(米国)、ワルシャワ(ポーランド)、バルパライソ(チリ)、ブリュッセル(ベルギー)でフィアレスシティ会議が開かれた。最近ではアムステルダム市、コペンハーゲン市が自治体決議を経てフィアレスシティの名乗りを上げた。
経済と労働分野の政策責任者であるピッサレロは「自治体にとって公共調達(※)はもっとも有力なツールである」と言う。公共調達において、自治体が人権侵害に加担する企業や脱税している企業を入札させないだけでなく、地域内の生産者組合によって生産された物やサービスを積極的に購入することで地域経済を振興することも可能である。
※公共調達:政府や地方自治体、政府機関が物品やサービスを購入すること。
エネルギーの再公営化を目指すグルノーブル
ルノーブル市は、フランスで2000年に水道サービスを再公営化したパイオニア。現在、同市は温室効果ガスの低減に向け、暖房や街灯などをすべて地元のエネルギーサービスで賄うべく再公営化することを目指している。再公営化は環境的な目的だけでなく、電気料金の支払いができない世帯を守る料金体系を設定する社会的な政策も可能にする。
学校給食についても常に公共の管理の下に置いており、さらに現在は地元産の100%有機食材使用を目指している。市が地元の農家と学校給食の食材提供の契約をしようと思ったところ、EU単一市場下の「公共調達指令」によって公開入札を義務付けるルールに直面した。
このルールによれば、市が地元の有機農産物を給食のために優先的に購入するのは差別的だということになり、画一的な給食サービスを提供する多国籍企業も入札させなくてはいけない。これに対しグルノーブル市は創造的な解決策を見出した。小学校の生徒が学習の一環で給食の食材がどこからくるのか勉強するために農場を訪問するので、地域内のサプライヤーでなくてはならないと唱え成功したのだ。
また、グルノーブル市は市民参加型予算制度(※)があり、オルモスは市議としてそれを担当している。この市民参加型予算の枠組みを使い、市民の要求が予算化されて、市立図書館の閉鎖を回避できたこともある。参加型予算は市民が地域の優先課題を話し合う重要なツールだと、オルモスは言う。
※市民参加型予算制度:自治体の予算配分を自治体職員ではなく、その自治体に住む住民が一部決定する制度。
対抗手段としてのミュニシパリズム
ミュニシパリズムの運動の新しさは、既存の政党という組織形態をとらず、具体的な変化を市民と共に起こすことにフォーカスしている点であろう。
まとめるならば、国家主義や権威主義をかざす中央政府によって、人権、公共財、民主主義が脅かされるつつある今日、ミュニシパリズムは地域で住民が直接参加して合理的な未来を検討する実践によって、自由や市民権を公的空間に拡大しようとする運動だといえる。
具体的には、社会的権利、公共財(コモンズ)の保護、フェミニズム、反汚職、格差や不平等の是正、民主主義を共通の価値として、地域、自治、開放、市民主導、対等な関係性、市民の政治参加を尊重する。ミュニシパリズムは普通の人が地域政治に参画することで市民として力を取り戻すことを求め、時にトップダウンの議会制民主主義に挑戦する。政治家には、地域の集会の合意を下から上にあげていく役割を100%の透明性をもって行うことを求める。
岸本聡子
きしもと・さとこ:環境NGO A SEED JAPANを経て、2003年よりオランダ、アムステルダムを拠点とする「トランスナショナル研究所」(TNI)に所属。経済的公正プログラム、オルタナティブ公共政策プロジェクトの研究員。水(道)の商品化、私営化に対抗し、公営水道サービスの改革と民主化のための政策研究、キャンペーン、支援活動をする。近年は公共サービスの再公営化の調査、アドボカシー活動に力を入れる。著書に『水道、再び公営化! 欧州・水の闘いから日本が学ぶこと 』(集英社新書)
ーー
岸本聡子 ヨーロッパ・希望のポリティックスレポート #maga9
第1回:ミュニシパリズムとヨーロッパ その1
第2回:ミュニシパリズムとヨーロッパ その2
第3回:学校ストライキ!中高生たちが起こす反気候変動の地殻変動
第4回:ベルリン住宅革命前夜
第5回:選挙ラッシュを終えて、スペイン地方革新政治の行方
第6回:イギリス混迷のなか、労働党大会にみた市民の力
第7回:再公営化の最前線発表~アムステルダム市と「公共の力と未来」会議~(岸本聡子)
第8回:コロナ騒動のなか、あえて難民危機と国家について考える
第9回:コロナ危機下で人々の暮らしをどう守るのか(岸本聡子)
番外編(下):【オンラインで聞きました】「経済補償のポイントは?」「緊急事態宣言は必要?」マガジン9スタッフとの質疑応答
番外編(上):【オンラインで聞きました】公共サービスを守り、不安定雇用をなくす:コロナ危機後に必要な変化
第10回:パンデミック後の社会:経済と環境を同時に回復させられるか
第11回:自治体からのグリーン・リカバリー:ブダぺスト、プラハが物申す
第12回:フランス地方選挙で起きた「躍進」――市民型選挙の戦い方を学ぶ
第13回:平均年齢44歳の新内閣。分断を越え、政治をアップデートできるのか
第14回:ミュニシパリズムとEUグリーン・リカバリー
第15回:闇か、希望か―分岐点に立つ欧州グリーンディール
第16回:アルゼンチン・ロサリオ:農と食、流通のミュニシパリズム的な革命
第17回:新型コロナウイルスのワクチンは「グローバル公共財」か
第18回:「命の経済」の回復~資本主義を問うフェミニストの視点から~
第19回:高騰する民間賃貸にNO! 住民投票で変革を起こす「ベルリンっ子」
第20回:気候変動ネットゼロにだまされない。「ジャスト・トランジション」を実践する公・コミュニティー連携
第21回:真の「チリの奇跡」が起きている
ーー
都市の公共財を守るために
「私がつかんだ #コモン と民主主義」著 岸本聡子 晶文社 バルセロナ市民がつくった新しい政党バルセロナ・コモンズのリーダー,アダ・コダール(バルセロナ市初の女性市長)「私たちは選挙をこえて都市の… https://t.co/pVZVwf1FOB
水道の民営化法案が国会で議論になっていた2018年、岸本聡子さんに大変お世話になった。ヨーロッパでは水道の再公営化が進んでいる。水道の民営化で多くの問題が起きたのである。法律が成立し地方議会が多数決で賛成すれば水道の民営化が可能。命の水を守ろうと言う運動をあらゆるところで作っていこう pic.twitter.com/pLWtQ5VliR
— 福島みずほ 参議院議員 社民党党首 (@mizuhofukushima) March 17, 2020

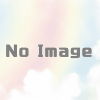

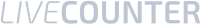
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません