大反対!小選挙区制:石川真澄
新聞、テレビがこぞって小選挙区制導入をはやした当時、創刊直後の週刊金曜日は反対の論陣を張っていた。石川真澄さん(元朝日政治部記者)の記事を再読した。
以下、月刊金曜日1993.10.22号より抜き書き。原文はこちら。
ーー
金権腐敗一掃は、どのように〝選挙制度改革〞にスリかえられたのか。
死票を増やし、独裁政治に道を開く「小選挙区制」がいいのだと、細川政権は言う。これは本当か。
「小選挙区制」論のカラクリを暴くー迷信が”常識”に化けるまで 石川真澄
五割の票をドプに捨て去りニセ多数派をつくり出すだけの小選挙区制。
ー 小選挙区制が「作られた多数派」つまりニセ多数派をつくりだし、民意を反映しないという根本的欠陥をもつことに関しては、石川真澄さんの「選挙制度」(岩波ブックレッット172号)が証明しています。
もともと政治腐敗をただすことが第一のはずが、それを選挙制度間題にスリかえたこと、スリかえで国民もだまされていることに基本的悲劇(喜劇?)があると思いますが、焦眉のこととして現に小選挙区制が強行されようとしている以上、これは対応せざるをえません。
・小選挙区制浮上までの舞台裏
-最も基本的な問題として「選挙とはだれのため、何のためにするのか」「国民のため、国会をつくるためにするのだ」-と石川さんは問いかけ、しかるに小選挙区剃推進者たちは「どんな『政権』をつくるか」に熱中している、と指摘されています。こんなことになってしまった始まりはどういう舞台裏からスタートしているんでしょう。
石川 一九九〇年の四月に第八次選挙制度審議会の答申が出ました。小選挙区比例代表並立制を一本にして答申した。
マスコミの代表をたくさん入れた。主な新聞や放送の社長・論説委員長・編集委員などOBを含めて。しかも、朝日新聞以外は全部、社長とか論説委員長というクラス。そのときの答申案の衆議院の選挙制度に関する答申の取りまとめをしたのが慶応大学教授の堀江湛さん。この人は慶応大学の法学部長もした。
政治学者として第八次審議会の委員になっていた人が三人いるんです。この堀江さんと、もう一人は東大の佐々木毅さん、それからいまは東海大学に移りましたけれども、その前は法政大学の内田健三さん、この三人が委員でした。
堀江氏は、はっきり目的意識的に「政確論」に重点を置いた。ですから、はじめから答申の内容がこれに偏っていたのは当然です。つまり、答申をよくご覧になると、選挙制度というのはどういうものがいいかということについて、その基準を示しているんです。
①まず第一に挙げたのは、政党・政策本位の選挙となるか。
②二番目に、政権交替が起こりやすいか。
③三番目が、その制度で政権が安定するかどうか。
④四番目が政権が国民の端的な意思によって選ばれるような選挙制度であるか。
⑤五番目に、少数意見をも反映できる制度であるかどうか。
②③④は全部「政権」という言葉がある。要するにはじめから「連立政権では嫌だ」ということ。
要するに「連立政権否定諭」。選挙の済んだ後で政党同士の話し合いによって政権が生まれるから、国民が直接選んだかたちにならないじゃないかという言い方ですね。
・小選挙区制か比例代表制か
そうすると、その当時の常識では「政権交替があるかどうか」といえば、当然「小選挙区制のほうが政権交替がある」と考えて、だれも異論を唱えない。二番目に政権が安定するかというと、それは単独過半数政権だから安定する。三番目に、いま言った連立かどうかの問題です。
この三つに関して「政権」本位に検討すれば、この三つとも完全に小選挙区制の勝ちになります。
選挙制度というのは基本的には小選挙区制と比例代表制しかないんですね。
それでは最初の①政党・政策本位かどうか。これはどっちもそうです。日本のいまの中選挙区制と比べるならば、いちおうその点は小選挙区制もそうですし、比例代表制も当然政党“政策の争いで出て行くので(後略)。
しかし第五番目の⑤「少数意見をも反映できる」という点は完全に比例代表制が勝ちですね。
これで総合判定をすれば、三勝一敗一引き分けになる(笑)。
はじめから五つの基準のなかに三つも「政権」を滑り込ませている。
どのように政権を作るかということに委員たちの関心が向いていたことがわかります。これがすべての始まりだと思うんです。いま進行中の選挙制度「問題」には、これだけの前置きが必要です。それ
では逆に、基本のほうの「いったい政権が大事なのか、国民の意思の縮図を作るほうが大事か」ということについてはしばらく措いておいて、いまの五つの判定材料について一つずつ考えていきましょう。
・「小選挙区制で政権交替」は迷信だ
私は朝日新聞の従業員だけれども、もう故人になった朝日の論説主幹の笠・信太郎さんとか森恭三さんとか、ああいう人々が戦後すぐの時期に「議会制の母国英国」-ということをしきりにおっしゃった。イギリスの政治くらいいいものはないと言っていた言葉に、もうみんな洗脳されているのね。
ところが、現代ではたくさんの学者がいろいろとこれに文句をつけています。いちばんポピュラーなのはジョヴァン二・サルトーリという、フィレンツェ出身のもともとはイタリアの学者なのですが、アメリカへ移った学者です。サルトーリの著書は、いま世界中で、これも政党理論の引用をするときには常に用いられているいちばんポピュラーな本です。
そのサルトーリがなぜそんなに信用されるのかというと、これは「説」ではなくて実証研究だからなんです。
その彼によれば、まず二党制(小選挙区制)というのは、どのように定義を緩めていっても、実際には世界中できわめて少ない政党制であることをまず第一に言っている。
さらにそれに続けて「それがもし政権交替という要素も入れて、政権交替がうまくいっているということも含めて、二党制が驚くほどうまく機能している国は世界中にただ一つしかない。言うまでもなくそれはイギリスである」。サルトーリのこの結論は七〇年代の終わりごろです。
ところが、その英国でさえ政権交替しなくなった。二党制でさえなくなってきつつあるということです。そうすると日本が仮に単純小選挙区制をとったところで、二党制になるかどうかも保証されていないし、二党制になったからといって政権交替が起こりうるということも実証されていないんです。意外なことに、小選挙区制だと政権交替が起こりやすいということは実証されていない。
アメリカ合州国の下院議員の選挙は、もう四〇年間、常に民主党が過半教の議席をとって勝っているでしょう。だからむしろ小選挙区制はほかの制度に比べて政権交代が起きにくい制度だと言ってもふしぎではないんですね。
・「小選挙区制で政権安定」も迷信だ
これはローレンス・ドッドという人の『連合政権考証』という本がサルトーリと同じころ出まして、これも実証研究なんです。この研究によりますと、連立政権は不安定で、単独過半数政権は安定政権だということは、一九世紀以来の長い間の迷信であったと、これははっきり書いている。つまり詞べてみると、四〇カ月以上続いた、要するに寿命の長い政府の七割以上が連立政権であったことが明らかになったということなんですね。おそらく世界中の学者が認めていると思います。だから二番目の命題もだめなんです。
その次の(④の)「政権が国民の端的な」という部分だけが、実はやや説得力があるんです。
- つまり(小選挙区制は)独裁政治にはいい(笑)。
石川 そうそう。国民が自民党に投票した結果だとして過半数で自民党政権ができる。そういうかたちのほうが端的だと言えば端的です。しかしこれとても、連立政権を作る側から言えば、もともと「政権をこういうかたちで作ります」と、はじめから言っている国ががなりあるんです。あるいは「自分のところはとても独自で多数は取れないから連立に加わるつもりもない、閣外協力でどこどこに協力する」とかいうことを選挙のときに有権者に公約していれば、その点の問題は避けられるだろうと思うんです。だから政治というのは制度とか法律とかだけですべてが決まるものではなくて、そのやりようだ。同じ制度でも運用によるということだと思うんですね。
・「イギリスの選挙制度はダメ」が常識
イギリスは、私がこの間「世界」に書いた文章で最初に引用したのですけれども、私の翻訳ですと-「何十年もの間、英国は悪い政治の下に置かれてきた。選挙制度のせいである。この制度によって有権者の過半数に至らない得票で選ばれた政府がほとんど絶対的な権力を握る。政治にプラグマティズムでなくイデオロギーが、対話でなく対決が持ち込まれる。そして膨大な量の中間的な有権者たちが不満のまま置き去りにされる。この制度は公正ではないし、効率的でもない」。こう書いてあるのは学説でも何でもなくて、今年四月二一日の日刊紙『インディペンデント』の社説の書き出しなのです。論証の必要がない。つまり常識になっているのです。
・八九年参院選の例をこらんなさい
実はこのときの選挙は、ある意味では実にいい具体例を示しているのです。私は参議院の選挙制度を基本的にはだめな制度だと思っていますが、こういう議論をするときには都合がいい。つまり参
議院の選挙制度というのは選挙制度のデパートなのですね。ご承知のとおり比例区があって、いま言った一人区すなわち小選挙区があって、二人から四人という中選挙区まで用意してある。あらゆる選挙制度が出そろっている。こういうときに同時に同じ人の心で選挙するわけですから、比較考量するには非常にいいんです。さてそこで、二六の小選挙区ではたしかに政権交替が起きていた。しかし「では中選挙区ではどうだったのか、比例区ではどうだったのか」も同時に見なければいけないわけです。そうすると、ここに数字が書いてありますが(別表)、中選挙区でも確実に政権交替は起きています。自民党は転落しちゃっているんですね。自民党対当時の野党で比べると、野党のほうが多い。比例代表区に至っては、もともと自民党は過半教の議席を得ていないけれども、このときの選挙ではなんと社会党が第一党になっているんです。社会党第一党、自民党第二党という結果が出ている。
ただし、小選挙区制だと政権交替はドラスチックに起きるんです。ドドーンとものすごく劇的になるから、みんなそれにワーッと目を奪われるけれども、あれだけ民意が、あのときは消費税が中心でしたけれども、ああいうふうにダーッと変わりさえすれば、選挙制度が何であれ政権交替が起きるんです。八九年選挙は非常に見事にそれを実証した、いい実例になる選挙たったのですね。
だから私は「比例代表になったら政権交替が起きます」なんて言わない。民意が変われば政権交替は起きる。これはごくあたりまえのことなんです。それを制度のせいで政権交替が起きたみたいに言うのは、まことにひどいごまかしなんですね。この言い方自体が、もう民意をいかに無視しているか。民意という言葉は古くてちょっとひっかかるんだけれども、人の政治意識というものについてまったく配慮しないで、まるで制度が変えたように言うわけですね。
制度が政権を変えたみたいに間違える。八九年選挙は、そういう意味ではすぼらしい実証例なんですよ。
・戦前の日本の小選挙区制の場合
たとえば日本は原敬内閣のころに小選挙区制を二回だけやりました。
これはもともと原敬が、政友会が過半数をとれないまま政権の座についたものだから、圧倒的な過半数を取ろうと思って、あのとき小選挙区制に変えたんです。思惑どおり圧倒的な過半数を取って、一党優位もすごいことになった。だからこのときも、小選挙区制はもともと政権交替を目指したのではないんですね。与党権力を大きくしようという狙いでしかない。
昭和のはじめまでが、いちおう日本の緊政治の形がやや完成した時期です。その時期の選挙制度が実は中選挙区制だったんですね。だから政党制と選挙制度との関係というのも怪しいし、まして政権交替が起きる起きない、政権が安定するなどということと小選挙区制が結ぴつくなどという俗説は、まったく証拠がない。おおげさに言うと、古今東西ないわけだから(笑)。
ただ選挙制度というのかちょっとやっかいなのは、選挙制度と教育問題とは似ていると僕はよく言うんですけれども、みんな知っている気になっちゃうんですよ。
ほんとうはそうとう専門的に勉強しないと教育問題の評論はおそらく非常に難しいことだろうと思うんですね。
半可通というか、知った気になっていて、そこへもってきて政治記者なんていうと、何かいっぱしの専門家の気になって実はいま言った第八次選挙制度審議会委員なんかになった新聞社の社長とか論説委員長とかはたいていは政治記者出身ですよ。だから彼らは選挙制度についてはおれはいっぱしわかっているというつもりになっているわけ。ところが、まあ悪いけど…。
ー政治業界記者だから…。
社長とか論説委員長とかになる人はそんなことを深く勉強したことないよ。勉強していたら、なれないんじゃないかな。
-ジャーナリストじゃなくて情報産業のマスコミ人。
石川 こういう人たちが大きなことを言って、「英国ではなあ」なんて言っているわけね(笑)。
-これは政界と報道界がグルになっての詐欺(笑)。
朝日新聞にも四年ぐらい前に、ちょっと早過ぎるんだけれども、選挙制度とは何だというのを書いたことがあります。ところがふしぎなことに、だれも理論的に文句を言ってこないのです。理論的な反対論は一つもない。
・税金で「政党助成」は矛盾だらけ
私がもともと助成金に不信感をもったのは、旧西ドイツの選挙を二度か三度か見に行ったときです。あそこは社会民主党本部とキリスト教民主同盟の本部がボンにありますね。どっちもものすごく立派を建物で、すばらしい。ところが第三党の自由民主党に行きますと、建物がみすぼらしいんです。つまり党の大きさにちょうど合っているんですね。これは下手をすると助成金のせいじゃないかと私は思った。国庫補助がつく国というのは意外に少ないんですよ。ドイツとかスウェーデンとか、日本がありと敬意を払っている国が政党に対する助成金を出しているんで、反対するのはやりにくい面もあるけれど。この制度だと政党の勢力が固定しちゃうんです。
やっぱりお金があると運動をしやすいし、組織活動も活発にできますから。特にこのごろはテレビの電波を買うとか、そういうことに非常にお金がたくさん要ります。しかし大きい党でないとたくさんお金が入らない。大きい党はたくさんお金が入ってきて、より大きくなろうとする。小さい党は少ししかお金が入ってこなくて、小さいままでいることになる。ここに大きな問題があると、ぼくはドイツで思ったんです。
-しかも新党ができにくい。
そう。それがぼくが助成金はないはうがいいんじゃないかと思った最初なんです。ただこれは、それ以前の根本的問題として、税金を使うのに「何に使っても勝手」というのはたいへんなことですよ。
税金使って飲み食いしたり、場合によっては芸者の花代を払ってもいい。これはひどいと私は思うのね。やっぱり税金を使うということは、ほかの分野だったらたいへんですよね。
-共産党は憲法違反論ですね。
石川 うん。自分が支持していない政党のために自分の税金が使われるからね。
- 本来、政党というのはある種自由競争でなければおかしいものが、そういうことになっちゃうと一種の〝社会主義〝というか、そこだけが全然競争のないソ連型に……。
石川 そうなんです。
-一つにはこれが欲しくて小選挙区制にしたいんじゃないでしょうか。
石川 社会党なんかそうですね(笑)。ほんとうにこの政党助成が欲しいばかりに…。だから少し難しい問題があると思うのは、たとえば企業献金を一方で受けながら、それで助成を′受け取っているのはけしからんという説がありますね。それはそうだと思うんです。そうしたら、きれいごと
のほうだけ「税金で使いました」と言って、汚いほうは全部企業からの献金でやれば、報告のほうもきれいに行くでしょう。結局は金権政治は変わらないということが問題になっているんですが、では企業献金を完全に禁止して、そのかわりに税金で全部面倒を見てあげましょうというふうなことがほんとうにいいか。
ー別段の問題のとおり、原点に返って考えれば、政治は政党を作るためにあるのではなくて、人々が幸せになるためにあるわけですね。そのための競争はやっぱり自由でなければいけない。そうすると、国家からも企業からももらわないということが原則でなかったら、政治の理念は発展していかないような気がするんですね。その原点に立つべきではないかと思うんです。なぜどこかからお金をもらうことを前操に考えちゃうのか、その論理的な根拠は何なのですか。
・外国の企業献金問題
やっかいなのは、「政治にお金がかかるのはあたりまえだ」という前提です。政治家は雲や霞を食らっては生きていられない。政治には金がかかるのは当然だというんですよ。その金をどこから調達し、どのように使うかという問題になる。
世界中で「お金にきれいだ」ということがほとんどない。これが困る。
たしかに法律ではちゃんと歯止めが決まっているんですよ。たとえば、企業の政治献金はすべて株主総会に報告しなければならないわけですから、そのことによって公開されている。どの会社がだれに、どこにいくら出したというのはわかるはずになっているけれども、それでも抜け道があって、得体の知れないやつから金をもらったみたいな話はしょっちゅう出てきて、汚いことがいっぱいあります。どうもこれは制度をきちっとしさえすれば万事めでたしというんじゃなくて、年がら年中監祝したり、文句をつけたり、その党をおっことしたりということを常時やっていなければいけないということではないか。だから常にお金の問題は、ある日立派な法律ができて、それ以後きれいにをるということなど望みがないと思っているんです。
- これもまた制度の問題ではない。
石川 ないと思いますね。
-となるとジャーナリズムの役割は大きいと。
石川 そうなんですね。たしが朝日新聞は企業献金全廃の方向を出して。私は実はこれには首を
傾げているんです。税金から出すくらいならば、むしろ企業・団体献金を許しておいて、そのかわりガラス張りにする。圧倒的にガラス張りにする。いまの日本の法体系は実はそうなっているはずなんです。だから.どのようなかたちであれ、個人はもちろんだし、政党をどのようにして支援するかというのは自由である。原則自由ですね。ただしそれは細大漏らさず公開されなけれはならない。
ーいくら細かい金でも全部
そうそう。公開する。それがいいか悪いかということは国民が選挙で判断する。
どこの国でも、企業・団体献金を禁止しているところは実はないんです。意外にない。これも
どこでどう間違ってしまったのか、外国の例ばかり言うなと言われればそれっきりですけれども、事ほどさように難しいんです。
抜け道は筒単だし、抜け道を防ぐことは難しいと思うんですよ。だからそれよりも出と入りを完全にオープンにするように、いっぱい歯止めを作ることだと思うんです。ところがその意味で言うと、税金から出しておいて「使い道勝手たるべ」というのは、いくら報告書が出たって、その内容がうそでもいいと私は思うね。それだからかえっていけない。
・献金と情報公開法の関係
特にアメリカの場合には、これは感心だと私が思うのは、情報公開法という壮大な体系のなかの一つなんですね。すべての政治に関する情報は、公開されなければならない。その一環として、政治家の収入・支出も公開される。特に高級官僚の収入・支出も公開されていますからね。
ただ、それでさえアメリカではまだ問題があるんです。政府からの助成は個人にはないけれど、大統領選挙にはある。大統領選挙にお金がかかることはご承知のとおり、すごいでしょう。あれには助成が連邦政府から出ているんですね。それにしてもアメリカは電波を買うお金がすごいから、べらぼうなお金がかかるというので、問題だということになっています。
アメリカでもう一つの問題は、たとえばある特定の企業からばかりお金をもらっている議員がいますね。それを平気で情報公開しちゃうわけですよ。しかし公開した結果、問題は有権者がそれに対して的確に「あれは特定の企業の代理人みたいなものだから、次の選挙で落っことそうや」ということになるかどうかなんです。アメリカでもこれは問題で、案外落ちない。アメリカ下院の小選挙区制
では再選率が九〇%以上のことがしょっちゅうですから、落ちないことが多い。それが次の間題になってきている。つまり零細な個人が寄付をして、それで政治活動をしているよりも、まとまってゴソッと大きな会社がお金を払っていれば、それはそれで有権者は楽でいいーというふうな感じになってきて、情報公開すれば何とか機能するとは必ずしも限らない。肝心のいま言った歯止めが効くかどうかは、政治教育なり政治風土なりの問題になるから、やっかいはやっかいなんです。
・絶望的な日本の「公職選挙法」
日本のように禁止だとか、陰に隠れてならいいとかいうふうな実態よりは、原則自由、公開、そして監視とチェックというシステムのほうが、原則としていいような気がするんですね。ただし、これは議論の余地があるところです。
どうも日本は何でも禁止というのか好きですね。.公職選挙法自体がもともと全部止。
公職選挙法だけは総司令部(GHQ)がほとんど手をつけていないんです。婦人参政権以外はほったらかしになった。
戦前の内務省が決めた選挙制度というのは、要するにあまり選挙をやってほしくなかったのね。議会そのものもあまり好きじやないし、選挙も困るし、特に普通選挙なんかになったら、〞アカ〞や何かが勝手なことをほざいて、議会に出て来て変なことを言われてはかなわない。だからほんとうはやってほしくな.だから、もうめちゃくちゃに全部禁止したんです(笑)。「選挙運動は原則的
にいけない」としちやった。ただし、選挙の公示から後は選挙運動をやってもいいという、そういう体系なんです。
包括禁止ですから。演説することを許すとか、ポスターは何枚まで許すとか全部禁止のなかに「やっていいこと」をみんな列挙しなければならない(笑)。
・民意と逆になる小選挙区制
「創価学会は、いまのまま公明党が五〇人とか六〇人程度の規模でそれ以上増えない場合には、これは国会のなかの一割の勢力でしかない。ところが新生党と一緒になり、いざの連立与党のなかで、あれあれは何も新生党だけではなくて、社会党に応援しても構わないんだし、新党さきがけに応援しても構わない。つまり創価学会の会員は至るところにいる。その連中がまとまって連立与党側の党を応援すれば、与党か野党かは別として、少なくとも政権を担いうる勢力を半分引き受けることになる。われわれが付いたほうが勝つかもしれない」ということで、一割しか影響カをもたない党が存在するよりも、五割の党に対してカを持つほうが、はるかに政治的影響力が大きいーという戦略を、僕は学会にごく近い人から聞いています。
ー小選挙区制の場合は死に票の問題、死んでしまう票が多い問題はどうなるのですか。
石川 死票という言い方をすれば五割以上死票ですからね。ただ、このごろわりと死票批判が出ないのは、自民党がこれに反撃したんです。反撃した理論は、「死票死票と言うけれども、たしかに選挙轄果だけを見れば死票に逮いないが、この背後にある緊張感で、当選した者は一生懸命に努力して、批判票つまり自分に反対する票が五割ぐらいあるんだということを念頭に置いているからまじめなことをする。死票が少なくて楽々と当選したりすればそうはいかないんだ」という説。ほとんど詭弁に近い。私は新聞にも書きましたが、イギリスの例で、得票数が少ないほうが政権についたことが二度あったというのはすごいことでね。この点で日本の憲法学界には、いったい日本国憲法が許す選挙制度は何かという議論があったんです。たしかに日本国憲法は一義的にどの制度でなければならないとは言っていない。ただし、最も憲法適合的である制度が比例代表制であり、最も
憲法不適合的な制度が小選挙区制であることは、憲法学界でもほほ合意があるんですね。なぜかというと、議席における多数派が得票数における多数派でなければならないということは、憲法の要請する最下限(ローワー・リミット)だというんですね。議席では多数派だけれども、得票数では比較少数であるというのはだめだ。
-少なくとも同じ以上でないと。
石川 そうそう。ところが小選挙区制だとこの逆転が起きてしまう。並立制だとこれがやっかいなんですね。どうなるかわからない。小選挙区のほうではこうだけれども、比例代表のほうではこうだというふうに、民意がはかり難い場面が出てくるかもしれませんからね。
・日本の中選挙区制は案外民主的です
世界中の選挙制度は小選挙区制が比例代表制か、どちらかに分類されること。
ただ日本の中選挙区制は実はそのどちらでもない。これは世界に一つしかない制度なんです、
選挙というのは、えらい子供っぽいことを説明して悪いんだけれども、まず投票の仕方と、当選者の出し方と、二通りの行為で成り立っていますね。したがって投票の仕方が単数か複数か、一人の名前を書くのか、複数の名前を書くのか。政党に投票というのは複数に投票したことになりますから、単数か複数かなんです。
ー選挙区は日本全国でもいいし、小さな村でもいい。とにかく選挙区というものを作らなければならない。いずれにしても選挙区を作って、その選挙区のなかでの当選者が単数か複数かを区別するんです。
これを組み合わせると、単ー単というのか小選挙区制なんです。一人に投票して、一人当選する。複-複というのか比例代表なんです。複数の名前に投票して、複数の当選者が出る。そうすると理論的には、一人の名前を書いて、複数の当選者ができるのと、複数の名前を書いて一人の当選者しか出ないのとありうるんですね。その「理論的にはありうるけれども世界に一つしかない」のが、一人の名前を書いて複数の当選者が出るという日本の制度なんです(中選挙区制)。
ーそうすると、その西洋人の考え方は案外民主主義ではなくて、日本がいまやっている中選挙区制のほうが、多様な人が出やすくて民主主義的だともいえるわけですね。
石川 そうなの。少なくとも結果的には、いまの日本のやり方のほうが少数派の代表が出やすいんです。
日本の制度(中選挙制)は結果的に、得票率と議席率が意外に接近しているんです。
・並立制の正体は小選挙区制だ
いま日本がやろうとしている小選挙区・比例代表並立制というのは明らかにこれは小選挙区制だというふうに分類される。小選挙区制中心の制度。
世界中に並立制が五つある。これはグラーベン方式と言うんですが、グラーペンというのはドイツ語の「溝」という意味。これは二つの制度を、間に溝があるまま、くっつけている。全然違う制度二つを同時に採用している制度という意味で「グラーベン方式」と言うんだそうですが、これが五つの国で採用されている。昨年の例では、韓国・メキシコ・ベネズエラ・セネガル・マダガスカルと、この五カ国。
並立制は大統領の下ではさして問題がない。
だけど日本のように、それこそ議院内閣制で、ここで問題が最初に戻ってくるわけです。堀江さんたちが言うように、議会の信任が最終的に大きな権限を持つ議院内閣制であることを重視したら、実は逆に並立制はとりにくいんじゃないかと僕は思うんです。なぜなら実例として世界中で五つしかないこの制度をとっている国が、五つとも一つの例外もなしに大統領制であるというこで、ほぼ見当がつくんじゃないでしょうか。大統領制では、議会で一党支配が続くことと政権が独裁化することがイコールではありませんからね。だから以上で選挙制度審議会をはじめ、小選挙区制や並立制推進論者たちの論拠は全部ひっくり返っている。議院内閣制であることを重視しても、この方式はとれない。
-単に独裁政治には都合がいいだけの制度になる、と。(引用終わり)
<まとめ>
・「小選挙区制で政権交替」は迷信だ
・「小選挙区制で政権安定」も迷信
・小選挙区制は独裁政治にはいい
・「イギリスの選挙制度はダメ」が常識
有権者の過半数に至らない得票で選ばれた政府がほとんど絶対的な権力を握る。
この制度は公正ではないし、効率的でもない.
・小選挙区制はもともと政権交替を目指したのではない。与党権力を大きくしようという狙いでしかない。
・税金で「政党助成」は矛盾だらけ。
この制度だと政党の勢力が固定する。
・民意と逆になる小選挙区制
議席では多数派だけれども、得票数では比較少数であるというのはだめだ。ところが小選挙区制だとこの逆転が起きる。
・日本の中選挙区制は案外民主的
中選挙区制のほうが、少数派の代表が出やすい。得票率と議席率が意外に接近している。
・小選挙区/比例代表並立制の正体は小選挙区制だ。
・議会の信任が最終的に大きな権限を持つ「議院内閣制」であることを重視したら、逆に「小選挙区比例代表並立制」はとりにくい。単に独裁政治には都合がいいだけの制度になる。
<小選挙区導入後の 衆院選投票率など>
第二次安倍政権は、自民の絶対得票率1割台で6割超えの議席占有率のペテン!
小選挙区制廃止を!
#自民党 スカ #菅政権 許す #小選挙区制廃止
第2次 #安倍 以降3回総選挙で #絶対得票率 と議席占有率の差は3倍越え,平均3.6倍超。
#投票率 50%台,#棄権 #有権者 が #自民 支える
#衆院選 #選挙に行こう… https://t.co/Ev7rWsIo7w
#自民党 が #財界 #独占資本 の代弁者であり、その資金によって動く党であることは単純明快な事実にすぎない」
別動隊 #維新 設立者は #竹中平蔵
#衆院選 #自民公明維新には絶対投票しない
#選挙に行こう
#棄権 が… https://t.co/ucsZPZIDMa
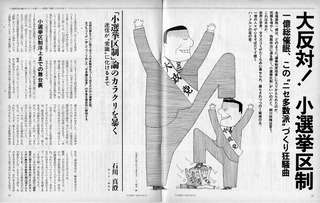



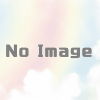
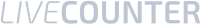
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません