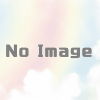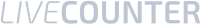社会思想史講義:新評論、山中隆次ほか著
P128 初期社会主義 英ブレイ「ユートピアからの航海」「女性は社会生活全般にわたって未開放であり(略)。日曜ごとに牧師から現体制の賛美を聞かされ、わが子に現体制の賛美を吹き込み、支配の再生産を行う役割を果たさせられている。従って女性の解放は社会変革にとっても決定的な意義を持つ。
*7章マルクス(1818-83)
・科学的社会主義:剰余価値の理論→「経済学批判」
「経済学哲学草稿」エンゲルスの私的所有の法則+労働疎外論
→「ドイツイテオロギー」分業と所有関係を基軸とする唯物論的歴史観
→「哲学の貧困」資本主義経済の分析→「賃労働と資本」→「経済学批判要綱」「経済学批判」→「資本論(第一巻)」
・唯物論的歴史観:ヘーゲルの社会と国家の関係、人間自己疎外 唯物史観=史的唯物論 生産ー交換ー分配における人間の社会関係と生産様式がすべての人間社会存立の土台となす。その上に、法的、政治的、科学的、道徳的、芸術的、宗教的思想など一定の社会的意識形態(イデオロギー)が上部構造として形成されるとみる。人間の社会的存在が究極において意識を規定するとの立場。
(山中隆次)参考文献:内田義彦「資本論の世界」岩波書店
*第8章アナキズム:自由の原理→近代国家の否定、自主管理論、自由社会主義、地域主義、連合主義にも脈うつ。
第3節バクーニン露(1814-76)実践家「国家は悪である」←権威であり、暴力。「人間の意思の合法的強制者であり、人間の自由の恒常的な否定者」
・第一インターナショナル(1864国際労働者協会)でのマルクスとの対立
国際社会主義運動の当面の目標:マルスク=私的所有の廃絶に求める
バクーニン=国家の廃止に求める。プロレタリア独裁が「人民から選出された少数の代表者による人民統治であり、「少数統治者の専制」と考える。「国家があるときは、必ず支配があり、奴隷制があるから」
「国家と無政府」独裁ではなく国家の即時的廃止と労働者の「下から上への自由な組織」(「国家と無政府」1873)
プルードンから示唆をえた「連合主義組織」→パリコミューン、BUT経済組織の変革についての原理的な掘り下げが乏しい。
あくまでもビスクマルクの中央集権的ドイツ帝国からのスラブ人の解放(汎スラブ主義)に起因していた。参考文献:E・H・カー「バクーニン」2巻1965現代思潮社ほか(藤田勝次郎)
(以下、更新中)
第2節プル-ドン
第10章マックス・ウェーバー
*キエルケゴール
*ニーチェ
*第2インターとレーニン
*ローザルクセンブルク
*第2インターと第一次世界大戦
*第3インター(コミンテルン)と社会主義インター(第2インター)の対立
〇西欧マルクス主義
1)ルカーチとコルシュ
2)フランクフルト学派
3)グラムシ
4)ハーバーマス